動画制作会社の選び方徹底解説|目的別で最適な選び方を伝授
- 2025年1月31日
- 読了時間: 23分
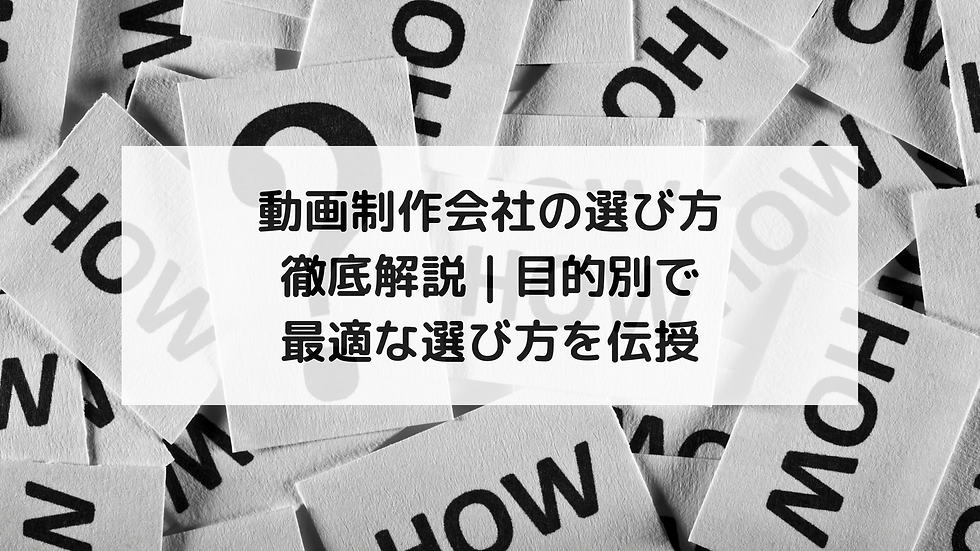
▶︎1. 動画制作会社とは?

1.1 動画制作会社の役割とサービス内容
動画制作会社は、企業や個人が目的に応じて必要な動画を企画から完成まで一貫してサポートする専門家です。単に映像を作るだけでなく、クライアントの目的を達成するために効果的な動画を提供することが役割です。以下では、具体的な役割とサービス内容をご紹介します。
動画制作会社の主な役割
企画立案
動画の目的や視聴者のターゲットに合わせて、アイデアを形にする段階です。「新商品の魅力を伝えるプロモーション動画」や「企業イメージを伝えるブランディング動画」など、具体的なゴールに向けてストーリーや構成を考えます。
撮影と編集
映像を撮影する技術や機材を駆使し、美しい映像を撮ります。その後、編集ソフトを使って、映像の流れや見せ方を調整します。視聴者の目を引くための特殊効果や音声の調整もここに含まれます。
アニメーション制作
実写だけでなく、アニメーションやモーショングラフィックスを用いて情報を伝えることも得意分野です。例えば、サービスの仕組みを視覚的に説明したり、キャッチーなビジュアルで商品を目立たせるときに効果的です。
配信サポート
完成した動画をどのプラットフォームで配信するべきかを提案したり、効果的に拡散するためのアドバイスを行います。YouTubeやInstagramなど、各媒体に最適化された動画形式やデザインをサポートすることもあります。
提供される主なサービス内容
動画制作会社が提供するサービスは多岐にわたります。プロモーション動画やSNS向けのショート動画、研修や教育用動画、イベントの記録映像など、目的によって異なる種類の動画を制作してくれます。また、制作した動画の利用方法についてもサポートしてくれることが多いです。
動画制作会社の魅力は、専門的な知識とスキルを活かして、クライアントの意図を最大限に形にしてくれる点です。 初めて依頼する場合でも、相談しながら進められるので安心感があります。
1.2 動画制作会社を利用するメリット
動画制作会社を利用することで、プロの力を借りながら高品質な動画を作成できます。個人や社内で動画を作る場合とは異なり、専門知識や経験が豊富なプロが関わるため、以下のようなメリットがあります。
1. 高品質な動画が作れる
動画制作会社は、専門的な機材や技術を駆使して、視覚的にも音声的にもクオリティの高い作品を提供します。特に、商品やサービスの魅力を最大限に引き出すプロモーション動画や、ブランドイメージを強化する企業PR動画では、「プロが手掛けた感」が視聴者の印象を左右します。
2. 効率的なスケジュール管理が可能
動画制作は企画から完成まで多くの工程があり、時間がかかるものです。しかし、制作会社に依頼することで、各工程を効率的に進めてもらえます。撮影や編集のスケジュールも管理してくれるため、クライアントは制作の進行を安心して任せられます。
3. 専門知識に基づいたアドバイスがもらえる
自分たちで考えるだけでは気づかないポイントも、制作会社なら適切なアドバイスをしてくれます。例えば、
ターゲットに響くストーリーの提案
動画の長さやフォーマットの最適化
使用する音楽やナレーションの選定
こういったサポートにより、より効果的な動画が仕上がります。
4. 幅広い動画の種類に対応できる
個人や社内では難しい、アニメーションやCGを使った動画も制作会社に頼めばスムーズです。また、SNS向けの短い動画や企業の研修用動画など、目的に応じた幅広い種類の動画を作れるのも大きな魅力です。
5. 動画の配信や活用についての提案が受けられる
完成した動画をどのように活用すればよいかについてもアドバイスをもらえます。YouTubeやInstagramといった配信プラットフォームに適した形式や、効果的な配信方法を提案してくれるので、動画の効果を最大限に活かすことが可能です。
プロに任せることで、クオリティ・効率・活用面すべてにおいて安心感が得られるのが、動画制作会社を利用する大きなメリットです。
▶︎2. 動画制作会社を選ぶ際のポイント

2.1 制作実績の確認方法
動画制作会社を選ぶ際、制作実績の確認は欠かせません。 実績をチェックすることで、その会社がどのような動画を得意としているかや、依頼する目的に合う動画を制作できるかが判断できます。
まずは、会社のウェブサイトやSNSで公開されているポートフォリオを確認しましょう。特に、自分が依頼したいジャンル(プロモーション動画、教育動画など)の実績があるかをチェックすると安心です。また、映像のクオリティや編集技術、演出の工夫にも注目しましょう。
さらに、自社と同業種の事例があるかも重要なポイントです。業界特有の特徴を理解した動画を作れる会社であれば、完成度が高い仕上がりが期待できます。実績に関する具体的な情報は、直接問い合わせて確認するのもおすすめです。
制作実績をしっかり確認することで、理想の動画制作に繋がります。
2.2 得意分野と対応可能な動画の種類
動画制作会社には、それぞれ得意分野や対応できる動画の種類があります。 自分たちの目的に合った会社を選ぶためには、その会社の強みを事前に把握することが大切です。
例えば、商品の魅力を伝えるプロモーション動画を依頼するなら、映像クオリティやマーケティングの知識が豊富な会社が適しています。一方で、社員教育や研修用動画では、わかりやすい構成や字幕、図解を得意とする会社が向いています。また、SNS用ショート動画では、トレンド感やテンポの速い編集が得意な会社が効果的です。
得意分野を見極めるためには、制作実績を確認したり、直接ヒアリングを行うのがポイントです。依頼する動画の種類に合った会社を選ぶことで、目的に合った高品質な動画を制作できます。
2.3 予算と費用感の把握
動画制作を依頼する際には、予算と費用感を把握しておくことが重要です。 動画の種類やクオリティ、規模によって費用は大きく異なります。
例えば、プロモーション動画では企画・撮影・編集などを含めて数十万円~数百万円程度が一般的です。一方で、SNS用ショート動画はテンプレートを活用すれば、数万円~数十万円で制作可能な場合もあります。アニメーションやCGを使った動画は、さらにコストが高くなることがあります。
制作会社に見積もりを依頼する際は、料金に含まれるサービス内容や修正対応の回数も確認しましょう。また、追加費用が発生する条件についても事前に話し合うことが大切です。
明確な費用感を共有することで、予算内で満足のいく動画を制作することができます。
2.4 コミュニケーションの取りやすさ
動画制作を成功させるためには、制作会社とのスムーズなコミュニケーションが欠かせません。 担当者がこちらの意図を正しく理解し、柔軟に対応してくれるかを確認しましょう。
まずは、問い合わせ時や打ち合わせの際の対応力をチェック。レスポンスの速さや丁寧なヒアリングがある会社は、進行中のやり取りも安心です。また、オンラインミーティングやチャットツールを活用できるかも重要なポイントです。リアルタイムで相談しやすい環境を整えている会社は、効率よく進められます。
さらに、修正やフィードバックを伝えやすい雰囲気を持つかも確認しましょう。気軽に相談できる制作会社を選ぶことで、理想の動画に近づけることができます。
2.5 修正対応と納期の柔軟性
動画制作では、修正対応と納期の柔軟性が重要なポイントです。 理想の仕上がりにするために、制作途中でのフィードバックや修正がスムーズに行える会社を選びましょう。
修正対応の範囲や回数については事前に確認が必要です。「2回まで無料」「テキスト変更のみ対応」などのルールを把握しておくと安心です。また、大幅な修正が必要な場合の追加料金も明確にしておきましょう。
納期についても、スケジュールの提示があるか、短納期案件に対応可能かをチェックすることが大切です。撮影や編集でトラブルが発生した場合に柔軟に調整してもらえる会社なら、スムーズな進行が期待できます。
修正対応や納期に柔軟性のある会社を選ぶことで、安心して制作を進められます。
2.6 制作後のサポート体制
動画制作は完成後のサポート体制も重要なポイントです。 動画を最大限活用するためには、運用やトラブル対応がしっかりしている会社を選びましょう。
まず、配信方法や活用のアドバイスをしてくれるか確認しましょう。YouTubeやSNSでの効果的な配信方法、最適なフォーマットの提案などがあると心強いです。また、完成後に追加の修正やアップデートが必要になった場合の対応力もチェックしておきましょう。
さらに、トラブル発生時のフォロー体制も大切です。データの再送付や再生不良時のサポートなど、万が一の時に頼れる会社なら安心です。
制作後のサポートが充実している会社を選ぶことで、動画の活用効果を高めることができます。
▶︎3. 自社に最適な動画制作会社を見つけるために

3.1 目的とKPIの明確化
動画制作を成功させるには、まず「動画の目的」と「達成すべき目標(KPI)」を明確にすることが大切です。 このステップをしっかりと行うことで、制作会社への要望が伝わりやすくなり、完成した動画の効果を最大限に引き出すことができます。
1. 動画の目的を明確にする
まずは、動画を制作する目的をはっきりさせましょう。目的が明確でないと、制作の方向性がぶれてしまい、期待する結果が得られないことがあります。目的の例としては、以下のようなものが挙げられます:
ブランド認知を高める
企業や商品の存在を広く知ってもらうための動画。たとえば、SNSでのシェアを狙った短いプロモーション動画など。
商品の購入促進
商品の特徴や使い方を魅力的に伝えることで、購入を後押しする動画。ECサイトやランディングページで使用されることが多いです。
社内教育や研修
社員や新入社員向けに、業務内容やルールをわかりやすく伝える動画。効率的な教育が目的となります。
採用活動の強化
求職者に企業の魅力を伝え、応募意欲を高めるリクルート動画。企業文化や働く環境をアピールします。
2. KPIを設定する
目的を達成するためには、具体的な目標(KPI:Key Performance Indicator)を設定することが必要です。 KPIを設定する際には、以下のような基準を考えます:
再生回数や視聴時間
「動画の視聴回数を1万回以上にする」「平均視聴時間を60秒以上にする」など、視聴データを基準にした目標。
エンゲージメント
「SNSでのシェア数やコメント数を増やす」「クリック率を5%以上にする」といった、視聴者の反応を基準にした目標。
成果の具体化
「動画を通じて商品購入につながるコンバージョンを200件以上獲得する」など、最終的な成果を指標とする目標。
3. 制作会社と目標を共有する
目的とKPIを明確にしたら、制作会社と共有することが重要です。制作会社は、これらの情報をもとに企画や提案を行い、目標達成に向けた最適な動画を制作してくれます。たとえば:
再生回数を重視する場合、視聴者の目を引くキャッチーな演出を提案
商品購入を促進したい場合、購入意欲を高めるストーリー設計を提供
3.2 ターゲット視聴者の設定
動画制作を成功させるためには、視聴者のターゲットを明確に設定することが欠かせません。 誰に向けて動画を作るのかをはっきりさせることで、メッセージが伝わりやすくなり、目的達成の効果を最大化できます。ここでは、ターゲット視聴者を設定する際のポイントをご紹介します。
1. 理想的な視聴者を具体的にイメージする
まずは、動画を届けたい「理想的な視聴者」のイメージを作り上げます。この段階で考えるべき要素は以下の通りです:
年齢層
例えば、10代向けにはトレンド感のあるデザインや音楽、40代以上には落ち着いたトーンが適しています。
性別
視聴者の性別により、デザインやメッセージのアプローチが異なる場合があります。
興味・関心
何に関心を持ち、どんな情報を必要としているのかをリサーチします。
生活習慣やライフスタイル
例えば、仕事中に見るのか、休日にリラックスして視聴するのかによって、動画のトーンや長さが変わります。
2. ペルソナを設定する
ターゲットをより具体的にするために、ペルソナ(仮想の視聴者像)を設定します。以下のように、1人の視聴者を具体的にイメージすると、動画の方向性が明確になります:
例)30代女性、都会で働くキャリアウーマン、趣味は旅行とカフェ巡り、日常の便利アイテムに興味があるこのペルソナを基にすると、「忙しい生活の中でも簡単に使えるアイテム」をテーマにした動画が適しているとわかります。
3. ターゲットの行動特性を理解する
視聴者がどのように動画に触れるかを考えましょう。
どのプラットフォームで視聴するか
YouTube、Instagram、TikTokなど、ターゲットがよく利用するプラットフォームに合わせた形式やトレンドを意識します。
視聴時間や動画の長さの好み
忙しい視聴者には1分以内の短尺動画、じっくり情報を知りたい視聴者には3〜5分の説明動画など、長さを調整します。
4. 制作会社と視聴者情報を共有する
ターゲットが明確になったら、その情報を制作会社に共有します。
「どんな視聴者に刺さる動画にしたいのか」
「視聴者にどんな行動を起こしてほしいのか」
こうした情報を伝えることで、制作会社は視聴者に響くストーリーや演出を提案してくれます。
動画制作はターゲット視聴者を明確にすることで、内容の方向性が定まり、伝えたいメッセージがしっかり届くようになります。
3.3 活用方法と配信プラットフォームの選定
完成した動画を効果的に活用するためには、配信プラットフォームの選定と活用方法を明確にすることが大切です。 動画の目的やターゲットに応じて、最適なプラットフォームを選ぶことで、メッセージをより多くの人に届けられます。ここでは、活用方法とプラットフォーム選定のポイントを解説します。
1. 動画の目的に合った活用方法を考える
動画の目的によって、活用方法は異なります。以下は、代表的な活用例です:
商品の購入を促進したい場合
動画をECサイトやランディングページに掲載し、購入を後押しするコンテンツとして活用します。商品の使い方や特徴を具体的に伝える内容が効果的です。
ブランド認知を高めたい場合
SNSやYouTubeに動画を投稿して、広く拡散されることを狙います。インパクトのある映像やストーリー性を意識すると効果的です。
社内研修や教育に利用する場合
社員専用のイントラネットやeラーニングシステムを活用します。視聴履歴を管理できるシステムがあると便利です。
2. 配信プラットフォームを選ぶポイント
次に、どのプラットフォームを選ぶべきかを考えます。各プラットフォームの特徴を理解し、目的やターゲットに合ったものを選びましょう。
YouTube
幅広い視聴者にリーチできる最大規模の動画配信プラットフォームです。商品のレビューや企業PR動画、ブランドストーリーなど、長めの動画でも視聴されやすいです。
InstagramやTikTok
若年層をターゲットにした短尺動画の配信に最適です。リールやストーリーズを活用して、トレンド感のあるコンテンツを投稿すると、拡散されやすくなります。
FacebookやLinkedIn
ビジネス層や専門職をターゲットにした動画を配信するのに向いています。特にBtoBの企業PR動画や採用動画などで活用されることが多いです。
ECサイトや自社ウェブサイト
動画を商品ページやトップページに埋め込むことで、購買意欲を刺激したり、企業イメージを伝えたりする効果があります。
3. プラットフォームに最適化した形式で動画を作成
選んだプラットフォームに応じて、動画の形式を最適化することも重要です。例えば:
InstagramやTikTokでは縦型動画が基本
YouTubeやFacebookでは横型動画が主流
画面サイズやフォーマット、字幕の有無などもプラットフォームごとに調整が必要です。
4. 動画配信後の効果測定も忘れずに
配信した動画がどれだけ効果を発揮しているかを測定することで、次回以降の改善に繋げられます。
再生回数やエンゲージメント(いいね、シェア、コメント)を確認
コンバージョン率やクリック率を分析
視聴者の離脱ポイントを調査して、次の動画に反映する
3.4 参考となる動画の共有
理想の動画を制作してもらうためには、参考となる動画を制作会社に共有することが効果的です。 自分たちがイメージしている動画の方向性を具体的に伝えることで、制作会社も理解しやすくなり、仕上がりがイメージ通りに近づきます。ここでは、参考動画を共有する際のポイントをご紹介します。
1. 具体的な動画例をピックアップする
まずは、ネット上や過去に見た動画の中から、自分たちが「こんな動画を作りたい」と感じたものをいくつかピックアップしましょう。注目するポイントは以下の通りです:
映像の雰囲気やトーン
シンプルでクリーンなデザインが良いのか、派手で目を引くスタイルが良いのかを考えます。
使用されている音楽やナレーション
動画の雰囲気に合ったBGMやナレーションの有無なども重要な要素です。
編集の仕方や映像
効果スムーズなカット編集や、特殊効果の使い方に注目してみましょう。
2. 「良い点」と「好ましくない点」を明確にする
参考動画を共有する際には、ただ見せるだけでなく、どの部分が気に入っているのかを具体的に伝えることが重要です。また、「この部分は避けたい」という点もあれば伝えておきましょう。例えば:
良い点:「テキストが画面上に動く演出がわかりやすくて好き」
好ましくない点:「ナレーションが早すぎて内容が聞き取りにくい」
これにより、制作会社は「依頼者が求めるもの」を明確に把握しやすくなります。
3. 業界や用途に合った参考動画を選ぶ
参考動画は、自社の業界や用途に近いものを選ぶと、より具体的なイメージが伝わります。例えば:
商品プロモーションなら、他社の製品紹介動画
教育や研修用なら、解説やチュートリアル動画
採用動画なら、企業文化やオフィス紹介の映像
同業他社の動画を参考にする場合でも、完全なコピーではなく、自社らしさをどう加えるかを意識しましょう。
4. 動画のリンクやファイルを共有する方法
制作会社に参考動画を渡す際は、YouTubeやVimeoのリンクを共有するか、動画ファイルを直接送付します。可能であれば複数の動画を渡し、それぞれの特徴を伝えるとより効果的です。
5. 制作会社の提案力を引き出す
参考動画を共有した後は、制作会社の提案力を引き出しましょう。たとえば、以下のような質問をすると、より良いアイデアが出てくることがあります:
「この動画の雰囲気を活かして、もっと魅力的にするにはどうすればいいですか?」
「この業界で効果的な動画の事例はありますか?」
▶︎4. 動画の種類ごとに適した制作会社を選ぶには
4.1 プロモーション動画を依頼する場合
プロモーション動画は、商品やサービスの魅力を視覚的に伝えるための強力なツールです。 制作会社に依頼する際には、ターゲット視聴者や目的を明確にし、動画のゴールを共有することが成功の鍵となります。ここでは、プロモーション動画を依頼する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
1. プロモーション動画の目的を明確にする
プロモーション動画を作る理由を明確にしましょう。目的によって動画の内容やトーンが変わります。
商品やサービスの認知を広げたい場合
新商品やサービスを幅広い層に知ってもらうため、インパクトのあるストーリーやビジュアルを重視。SNSやYouTube広告向けに短尺の動画を作成することが効果的です。
購買意欲を高めたい場合
商品の特長や使用シーンを具体的に伝える内容に。ECサイトやランディングページに最適な構成を意識します。
ブランドイメージを向上させたい場合
企業のストーリーや価値観を反映した動画で、感情に訴える内容を目指します。長めのドキュメンタリースタイルも適しています。
2. 必要な要素を盛り込む
プロモーション動画に必要な要素を事前に整理し、制作会社に伝えましょう。
メッセージやキャッチコピー
動画を見た視聴者が何を感じてほしいのかを明確にします。シンプルかつ印象的なメッセージが鍵です。
商品の使用シーンや魅力的な映像
実際に商品がどのように使われるかを見せることで、視聴者に具体的なイメージを持たせます。
ナレーションやテキストの配置
音声だけでは伝わりにくい情報を、字幕やグラフィックスで補足します。
3. 動画のスタイルや雰囲気を決める
プロモーション動画のスタイルは、ターゲットや商品イメージに合わせて選びましょう。たとえば:
若年層向けなら、明るくポップなデザインやテンポの速い編集
高級感を出したい場合は、シックで落ち着いたトーンや高品質な映像
テクノロジー商品なら、CGやモーショングラフィックスを活用した未来感のあるデザイン
4. 配信プラットフォームを意識する
プロモーション動画を配信する場所によって、フォーマットや尺が異なります。以下を制作会社に相談しましょう:
InstagramやTikTokの場合、縦型動画で15〜60秒程度
YouTube広告の場合、横型動画で6〜30秒程度
自社サイトや展示会用の場合、高画質で詳細な説明を盛り込んだ長めの動画
5. 成果の測定も忘れずに
プロモーション動画は、配信後の効果測定も重要です。再生回数やクリック率、購入数などのデータを分析することで、次回の動画制作に活かせます。
4.2 研修・教育動画を依頼する場合
研修・教育動画は、社員や学生に対して効率的かつわかりやすく情報を伝えるために活用されます。 オンライン化が進む中で、研修用動画の需要はますます高まっています。ここでは、研修・教育動画を制作する際のポイントを解説します。
1. 研修・教育動画の目的を明確にする
研修や教育動画を制作する際には、目的を明確にしましょう。目的によって、構成や内容が大きく変わります。
新入社員向けの基本研修
会社概要や業務内容、企業文化をわかりやすく説明する動画が求められます。ナレーションや字幕を入れて、初めて視聴する人にも理解しやすくすることがポイントです。
技術的なスキルの習得
専門知識やスキルを学ぶための動画では、操作手順や具体例を示しながら、段階的に学べる構成が効果的です。
コンプライアンスやルールの周知法律や社内ルールに関する教育動画では、具体的なケーススタディやアニメーションを使って、飽きずに学べる工夫をします。
2. 視聴者に合わせた内容の設計
視聴者の知識や経験に合わせて、内容を調整することが大切です。
初級者向け
専門用語を避け、基本的な概念や操作を丁寧に解説します。イラストやアニメーションを活用すると、理解しやすくなります。
中級者・上級者向け
実践的な例や応用的な内容を取り入れます。リアルなシミュレーションや具体的な事例を挙げると効果的です。
3. わかりやすい構成とデザイン
教育動画は視聴者が集中して学べる内容であることが重要です。そのために:
短いセクションに分ける
動画を10〜15分程度の短いセクションに分けることで、視聴者の集中力を保ちやすくなります。
図表やアニメーションを活用する
複雑な情報を視覚的に伝えるために、グラフや図表を使ったり、動きのあるアニメーションを取り入れたりします。
クイズやインタラクティブな要素を含める
視聴後に理解度を確認できる仕掛けを加えると、学習効果が高まります。
4. 配信方法とアクセスのしやすさを考える
研修動画は、視聴者がどこからでも簡単にアクセスできるようにすることが大切です。
イントラネットやLMS(学習管理システム)で配信
動画の進捗を管理したり、再生履歴を記録できるシステムを利用することで、研修の効率が向上します。
モバイル対応の動画
スマートフォンやタブレットでも視聴しやすい形式にすることで、外出先や移動中にも活用できます。
5. 制作会社に依頼する際のポイント
研修・教育動画を依頼する際には、以下の点を制作会社に伝えるとスムーズです:
視聴者の職種やスキルレベル
必要な資料やデータ(マニュアルやガイドラインなど)
動画に盛り込みたい内容や事例
4.3 SNS用ショート動画を依頼する場合
SNS用ショート動画は、短い時間で視聴者の心をつかむことが重要なコンテンツです。 特にInstagramやTikTok、YouTubeショートなどのプラットフォームでは、目を引く動画が拡散されやすく、ブランド認知や商品PRに大きな効果を発揮します。ここでは、SNS用ショート動画を制作会社に依頼する際のポイントをご紹介します。
1. 短尺動画の特性を理解する
SNS用ショート動画の特徴を把握しておきましょう。限られた時間内で視聴者の興味を引きつけ、メッセージを伝える工夫が必要です。
尺は15〜60秒が基本
プラットフォームによって推奨される長さは異なりますが、短いほど再生されやすくなります。
冒頭数秒が勝負
最初の3秒で視聴者の注意を引く演出が効果的です。キャッチコピーやインパクトのある映像を使いましょう。
2. プラットフォームに応じた動画の形式
SNSプラットフォームごとに適した形式を選ぶことが重要です。制作会社には、どのプラットフォーム向けに動画を作るのかを明確に伝えましょう。
InstagramやTikTokの場合
縦型の動画(9:16)が基本。リールやストーリーズ用に適したフォーマットを採用します。
YouTubeショートやFacebookの場合
横型(16:9)でも対応可能ですが、最近では縦型の動画が拡散されやすくなっています。
Twitter(X)やLinkedInの場合
横型やスクエア型(1:1)が好まれることが多いです。
3. 動画の目的に応じた内容設計
ショート動画を作る目的を明確にし、それに応じた内容を制作会社に提案してもらいましょう。例えば:
商品の認知を高めたい場合
商品を使用するシーンを短く見せたり、キャッチーなコピーを加える。
キャンペーンやイベントの告知
締切や開催日を強調し、行動を促すメッセージを伝える。
ブランドイメージを伝えたい場合
ロゴやカラーを活用し、視覚的にブランドの個性を印象付けます。
4. 目立つ演出を取り入れる
SNSでは動画が次々と流れるため、視聴者の目を引くための工夫が求められます。
テキストアニメーション
強調したいメッセージやキーワードを動きのある文字で表現します。
BGMや効果音
トレンドに合った音楽や軽快な効果音を使うことで、動画の印象を強めます。
特殊効果やフィルター
色調補正やグラフィックを駆使して、プロフェッショナルな仕上がりにします。
5. 配信後の効果測定も意識
ショート動画は拡散力が高い分、効果測定がしやすいのも特徴です。制作会社に依頼する際は、どのような指標で効果を測定するのかも話し合いましょう。例えば:
再生回数やいいね数、シェア数
コンバージョン率やリンククリック数
コメントやリアクションの内容
▶︎5. まとめ:目的別で考える動画制作会社選び
動画制作会社を選ぶ際には、「どんな動画を作りたいのか」「その動画で何を実現したいのか」を明確にすることが重要です。動画にはプロモーション、研修・教育、SNS向けショート動画などさまざまな種類があり、それぞれに適した会社やクリエイターが存在します。
例えば、商品の魅力を伝えるプロモーション動画を作るなら、映像のクオリティやマーケティングの知識が豊富な会社が適しています。一方で、社員研修のための教育動画を依頼する場合は、わかりやすい構成や字幕、図解を得意とする制作会社が安心です。また、SNS向けの短尺動画では、トレンド感やスピード感のある演出が得意な会社を選ぶと効果的です。
動画制作会社を選ぶときには、制作実績や得意分野、対応力をしっかり確認しましょう。そして、自社の目的や予算に合わせた提案が受けられるかどうかを見極めることが大切です。
動画制作は目的や用途に応じた適切な会社を選ぶことで、その効果を最大限に引き出せます。 専門家と連携しながら、視聴者の心をつかむ動画制作を進めていきましょう。
▶︎動画制作のことなら株式会社CROSS BEE VISIONにお任せください!
理想の動画制作を実現するためには、信頼できるパートナー選びが重要です。株式会社CROSS BEE VISIONでは、豊富な経験と高い技術力を持つチームが、プロモーション動画、教育用動画、SNS用ショート動画など多様なニーズに対応します。お客様の目的に合わせた最適な提案を行い、期待以上の仕上がりをお届けします。
「効果的な動画を作りたい」「どんな動画を依頼すればいいかわからない」という方も、ぜひ一度ご相談ください!株式会社CROSS BEE VISIONが、最適な動画制作をサポートいたします。

コメント